Our Journey Of Uplifting Lives
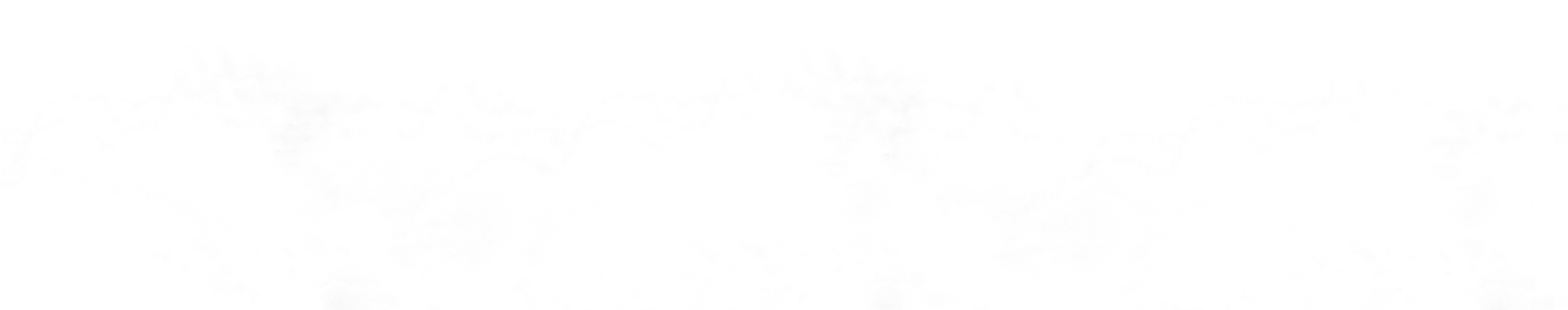
Welcome to Ecolife Foundation
Together we can be the change

15 Years of Transforming Lives, Thousands of Success Stories
Established in 2009, Ecolife Foundation has become an organization dedicated to enhancing the quality of life for underprivileged communities across India. With a team that started small but has grown significantly over 15 years, we strive to create lasting change by fostering self-reliance and leadership within the communities we serve.

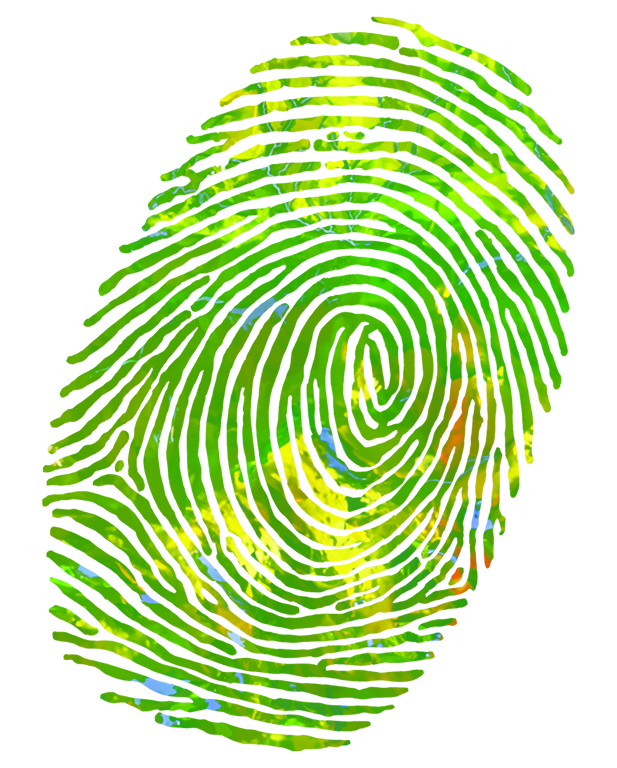
BELIEF
Making a difference doesn’t just require money or resources, it requires honesty, dedication, passion, and heartfelt emotions.
VALUES
Transparency, accountability, loyalty, and cooperation lie at the core of our mission, guiding every action we take.

CLEAN DRINKING WATER
- Access initiatives (HWFs, RO, etc.)
- 30,000+ beneficiaries
- Future target: 1 lakh by 2030

QUALITY EDUCATION
- Computer labs, infrastructure upgrades
- 50+ Schools | 10,025+ students

HEALTH & HYGIENE
- Sanitary pads, health camps
- 350,000+ pads distributed | 900+ camps
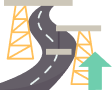
RURAL INFRASTRUCTURE
- Roads, bridges, water channels
- 40+ villages | 15+ water channels

SUSTAINABLE AGRICULTURE
- Organic farming, training, bio-inputs
- 8,000+ farms | 7 agri-centres

LIVELIHOOD DEVELOPMENT
- Skill training: sewing, goat rearing, etc.
- 3,000+ trained, 1,000+ under skill programs

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
- Solar lights, biogas plants, tree plantation
- 1.2 lakh trees, 1800 lights, 400 biogas plants
SOCIAL MOBILIZATION
- Farmer engagement, women empowerment, local participation
Impact Numbers

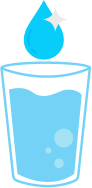

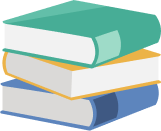

The Architects of Change

Monika Jaggia
Chief Development Officer, Ecolife Foundation

Amit Singh
Chief Executive Officer, Ecolife Foundation

Rohan Grover
Chief Executive Officer, Nature Bio Foods

Poppe Braam
Chief Executive Officer, Did It B.V.

Aart Jan
Managing Director, Leev.nu B.V.

Madeleine Kroger
Specialist Social & Supplier, Midsona AB

Vijay Arora
Chairman, LT Group

Dr. Rajeev Singh
Scientist, Agronomy, Jawaharlal Nehru Agriculture University
For NGO like ours, deeply rooted in India’s soil, we recognise the need to play a much larger role in creating growing societal value for the country given the colossal socio-economic challenges.
CATALYSING SYSTEMIC CHANGE BY CREATING MEANINGFUL INTERVENTIONS.
Testimonials
News & Press Coverage




